
東京に呼び込まれたオリンピック──この大会は何をもたらすのか
【緊急事態宣言下、無観客という異例の形で開催される東京五輪。この大会を五輪の歴史とともに振り返り、この五輪が日本に与える影響、問題を考察する】
石坂 友司(奈良女子大学)
現在、東京でオリンピック競技大会が開催されている。2021年7月8日、東京都に緊急事態宣言が発出されたのを受け、オリンピック(以後五輪と表記)の無観客開催が決まった。開会式の約2週間前に、開催都市の競技会場から観客がいなくなる異例の事態となった。五輪史上初めての延期と無観客開催を経験することになったこの大会を、五輪の歴史とともに振り返り、どのような問題が現出しているのかについて考えてみたい。
日本と五輪の出会い
1896年アテネで初めて開催された近代五輪と日本の関係は、1912年のストックホルム大会から始まった。当初は私的なサポートによって選手を送っていた日本だったが、1924年パリ大会より国庫補助が行われることになった。国家が世界のメダル獲得競争に参加することの意義に気が付いた瞬間だった。その後、次第に競技力をつけていった日本は、1940年大会の東京招致を計画し、嘉納治五郎らの尽力で招致成功を導いた。しかしながら、日中戦争に突入したことで、大会は返上せざるを得なくなり、いわゆる「幻の東京五輪」となった。
戦後、1948年のロンドン大会から再び歩みを開始した五輪は、1952年のソ連の参加によって東西冷戦という政治的対立構造に埋め込まれることになる。日本が再び大会招致を目論んだのが1952年、2度の挑戦を経て1964年大会の招致を勝ち取った。「東洋の魔女」と呼ばれる女子バレーボールチームの金メダル獲得など、史上最多の16個の金メダルを獲得し、大会は成功を収めたと評価された。経済成長期と符合する東京大会は、国際復帰を果たし、経済的に急成長する日本の姿を内外に示した強烈な成功神話とともに語られるようになる。スポーツをめぐる法整備(「スポーツ振興法」の制定)が行われ、トップスポーツの強化支援策の足場が築かれた大会でもあった。
この大会を当時の社会情勢と準備過程から分析すると、競技場や新幹線などの建設、インフラ整備などに不安を抱えていて、身近な生活から遊離したイベントとして国民の興味が薄かったことがわかっている(石坂友司・松林秀樹編、2018、『1964年東京オリンピックは何を生んだのか』青弓社)。また、組織委員会会長や事務総長の更迭などで組織は混乱していて、政治的中立を原則としてきたスポーツ界と国家、政治家との関係性が、後者に依存しながら強固に築かれていく様子をみてとれる。
一方で、大会の運営的成功とともに国民の多くが共有した成功体験は、いわゆる集合的記憶となって、以後の日本と五輪との親密な関係性を創りだしていく。そのことに大きく寄与したとされるのが、大会直前に全国を駆け巡った聖火リレー、小学校での競技観戦や、市川崑が制作した記録映画の鑑賞である。これらは2020年の東京大会にそのまま引き継がれるスキームとなっていく。
【引き続き「商業主義に開かれた五輪」に続く】

商業主義に開かれた五輪
創始期から参加の原則として採用されていたアマチュアリズムは、次第に時代にそぐわなくなっていった。開催都市は種目数や競技者数の増加により多額の開催経費を求められるようになり、プロが出場できないことで魅力や収益を高めることができず、赤字が生み出されていった。1976年モントリオール大会は、その赤字の大きさが都市の開催能力の限界にまで行き着いた大会である。次の1980年モスクワ大会は、米ソ両陣営が政治的に衝突し、アメリカや日本をはじめとする西側諸国のボイコットの場となった。
政治的対立が顕在化し、財政的破綻に向かっていた五輪は、ロサンゼルス大会から商業主義に開かれることになる。テレビ局が捻出する放映権料とTOPスポンサー(現在のワールドワイドオリンピックパートナー)からの収益を二本の柱に据え、プロ選手を参加させることでブランドを高める戦略が功を奏し、大会運営における見かけ上の収支バランスがとれることになった。
一方で、過剰な商業主義は、アマチュアリズムという金銭を求めない倫理観で運営されてきた大会の性質を歪めることになる。五輪は高額のテレビ放映権料を支払う、特にアメリカのテレビ局の意向を無視できなくなり、最適な気候や時間帯で開催ができなくなった。選手は時に過酷な環境下でのプレイを余儀なくされるとともに、テレビ映りの良い種目が優先され、ルールの改変も次々と起こっていった。2020年東京大会の自由を奪ったのも、このような商業主義の原則である。
レガシーの登場と開催経費の増加
国際オリンピック委員会(IOC)は大会のブランド力や収益力を高めることで存在感を増していき、国際競技連盟への支援を通じてさまざまな競技への支配力を強めていった。加えて、2003年以降は、立候補都市にレガシーと呼ばれる遺産創出のプランを練らせ、それを競わせることで開催都市に対する絶対的な優越を築き、不均衡な都市契約を結ばせることに成功する。
開催都市が掲げるレガシーを通じた魅力づくりは、壮大な競技場の建設、過剰な都市開発を生み、再び開催都市の財政を圧迫し始める。この間、五輪は女子種目を増やしていき、現在では男女がほぼ同数となったほか、若者の人気を獲得するために競技種目数も増加し続けている。その結果、開催経費がさらに大きくなり、2012年ロンドン大会、2014年ソチ大会でそれぞれ夏冬の最高額を更新した。東京が3度目の招致を目指した五輪は、このような状況下にあったのである。

国家的スポーツ戦略の展開
東京、日本が五輪招致に乗り出した理由の一つに、スポーツを通じた国家戦略の展開がある。2000年に策定された「スポーツ振興基本計画」は、その柱の一つに国際競技力の総合的な向上方策を掲げた。これは五輪でのメダル獲得率(全種目の総メダル数に占める日本が獲得したメダル数の割合)を1996年アトランタ大会の1.7%(金メダル数3個、総メダル数14個)から、10年で3.5%に倍増することを目指したものだ。2004年アテネ大会では、金メダル数が史上最多タイの16個、総メダル数37個で、メダル獲得率は3.98%となり、早々に目標を達成した。
また、2010年には「スポーツ立国戦略」が策定され、アテネを超えるメダル数の獲得など、世界で競い合うトップアスリートの育成・強化が掲げられた。グローバルな競争時代にあって、日本のプレゼンスを高める手段としてメダル獲得が位置づけられ、そのための強化費の増額、法律の整備(2011年「スポーツ基本法」の制定)、スポーツ庁の設置(2015年)などが矢継ぎ早に行われている。ロンドン大会では38個のメダルを獲得して目標をクリアすると、東京大会では25~30個の金メダル、総メダル数では70~80個が目指されてきた。圧倒的な数の多さに驚かされるだろう。
このように、ナショナリズムの高まりによって国民の一体感を演出しようとすることに加え、1964年大会の成功と成長神話の再現が目論まれ、課題として残されてきた都市問題を一気に解消しようとする再開発の意図によって、東京大会の招致が目指されていくのである。
東京五輪の招致
東京都は2016年大会の招致を目指して2006年から活動を開始した。この挑戦は失敗に終わったが、2011年に再び招致の声が上げられた。この年の3月には東日本大震災が起こっており、「復興五輪」という目標が掲げられることで、本来接点を持たないはずの五輪と復興が結びつけられてしまったのである。こうして2013年に呼び込まれた2020年大会の招致は、経済的意味と選手村からの距離を重ねた「コンパクトな五輪」に加え、復興を理念の一つに掲げてスタートを切った。
招致プランに書き込まれた予算案は本体工事費のみで、精査された全体の数字ではない。五輪経費が招致プランから大幅に増大することはほとんど全ての大会で見られ、東京大会も例にもれず倍額に膨らんだ。また、経費削減のために新たな競技場建設をとりやめ、既存施設を利用する方針に転換したことで、逆に会場は大きく広がり、コンパクトとは言えないものになってしまった。
一点補足をしておくならば、組織委員会が関わる大会運営経費は、コロナ禍がなければテレビ放映権やスポンサー収入などで賄われることになっていて、計画では回収が見込まれていた。残りの都の予算も競技場整備費などに充てられるものが含まれているため、全てが無駄なものとは言えない。大会経費は競技施設の維持・管理の状況などを見ながら今後検証する必要があり、いかに活用されるのかが問われるものである。

東京五輪が日本にもたらしたもの/もたらすもの
この大会が東京、日本に呼び込まれてきた背景を五輪の歴史や日本の事情から振り返ってきた。そこには五輪が掲げる「世界平和」といった理念があまり顧みられることなく、ナショナリズムを高める国威発揚型のイベントや、都市再開発の手段として期待が向けられてきたことが透けて見える。加えて、大会開催による知名度を利用したインバウンド(訪日外国客)の増加や経済波及効果への期待が同時に語られていた。
一時は多くの人に望まれた自国開催の五輪とその目論見は、コロナ禍の影響で無残にも打ち砕かれてしまった。大会は一年延期され、ほとんどの会場が無観客試合となったことで、チケット料収入を回収不能にしたほか、コロナ対策費として約3千億円の支出増加を引き起こしたことで、ロンドン大会を上回る過去最高額の大会経費となった。大会後は数千億円の赤字になることが予想され、東京に大きなダメージをもたらすことが確実な情勢である。
また、新型コロナウイルスの感染拡大が引き続く中での大会開催は、多くの人に不安を与え、それを強行しようとしてきたIOCや組織委員会、東京都、政府が批判の対象になった。加えて、IOCと開催都市が締結している不均衡な都市契約の存在や、IOCの強権的な態度に多くの人が気づくことになり、開催前に中止を求める機運はかつてないほど高まってきた。このような不安や批判を受けつつ、競技場では熱戦が展開されているものの、そこに応援する観客の姿はない。開催直前まで長引いた観客の有無の判断の遅れと、突然の有観客の取りやめは現場に混乱をもたらし、観戦を楽しみにしていた人びとにも失望を与えてきた。残念ながら、この大会は誰もが満足できない大会となってしまったばかりではなく、人々の分断とも言える状況を生んだ。
コロナ禍があったにせよ、50年、60年に一度の大会は期待とは大きく違うものになってしまった。当初から大会開催の遺産となることが期待されてきたボランティアやホストタウンの展開、小学校などでのオリンピック教育も十分な効果は期待できないだろう。唯一、アスリートの活躍の場を提供できていることは、五輪が継続してきた意義をつなぐ、開催都市としての責任を果たすことにはなっていると言えるかもしれない。
連日テレビを通して放映される自国開催の五輪を見ながら、この大会が私たちに何をもたらしてきたのか/もたらすのかについて考えている。それは、この大会の正負のインパクトと、私たちがこの大会に何を思い、どのような意義を見出したのか、あるいは見失ったのかについて検証することでしか明らかにできない。五輪との向き合い方を含め、大会の終幕とともに冷静な検証、議論が望まれる。
<執筆者略歴>
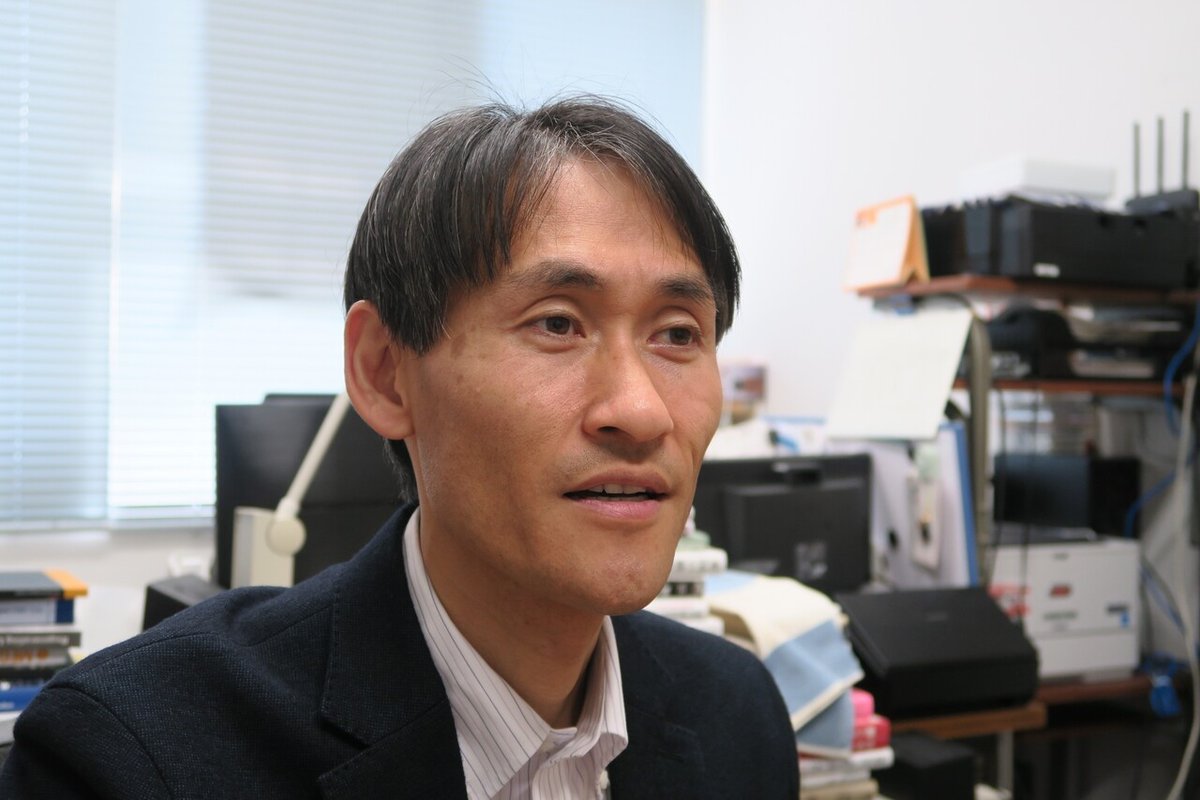
石坂 友司(いしざか・ゆうじ)
1976年生。奈良女子大学研究院生活環境科学系・准教授。専門はスポーツ社会学。著書に『コロナとオリンピック』(人文書院)、『現代オリンピックの発展と危機 1940-2020』(人文書院)、共編著に『未完のオリンピック』(かもがわ出版)、『1964年東京オリンピックは何を生んだのか』(青弓社)など。
この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。
chousa@tbs-mri.co.jp

