
日本の賃金を引き上げるために
【上がる気配の全く見えない日本の「賃金」。その根本的な原因はどこにあるのか。上げるためにはどうすべきなのか】
水野 和夫(法政大学教授)
なぜ賃金は下落し続けたのか―金融危機とグローバリゼーション
実質賃金は生活水準を表す最も適切な指標である。日本の実質賃金は1997年1-3月期をピークに下落傾向が続いている。2021年7-9月期時点でピークから15.9%(年率0.7%減)も下落した(名目賃金も同期間で年0.5%減)。1997年度以降2020年度までの間、実質GDP成長率は年0.5%でプラス成長だったのであるから、「成長あっても賃金への分配なし」で、「成長あって、資本への分配あり」だった。景気回復した時期でも賃金は下落しているのだから、成長如何にかかわらず賃金は下がるのがこの23年間の実態である。
実質賃金は労働生産性の増減によって決まるのが経済原則である。労働生産性は1997年度から2019年度の間、年0.6%増(日本生産性本部)だったから、労働価値が正当に評価されない状況が四半世紀近くにわたって続いていることになる。賃金が上がらなくなったのは、1990年代後半の金融危機によって企業が自己防衛するようになり、かつグローバリゼーションが世界的な潮流となった21世紀に入ると企業が国際比較されるようになって、その指標としてのROE(自己資本利益率)を重視する経営が大勢となったからである。ROEがもともと低かった日本は他の先進国よりも大幅な引き上げを迫られたため、賃金の上昇が抑えられた。
金融危機で銀行の貸し渋りや貸し剥がしにあった企業が手元流動性を厚くするために、具体的には現金・預金や短期有価証券を積み上げるために内部留保金を増やすことで企業は自己防衛を行った。金融危機が一段落すると、今度は欧米企業のROEは15-20%だから、政府はせめて8%に引き上げるように日本企業に要請した(2014年に経済産業省が公表した「『持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~』プロジェクト」)。2012年度の大企業・全産業のROEは4.2%、2013年度には7.4%だったが、2017年度には9.5%と経済産業省の要請である8.0%を上回った(2020年度は5.8%)。
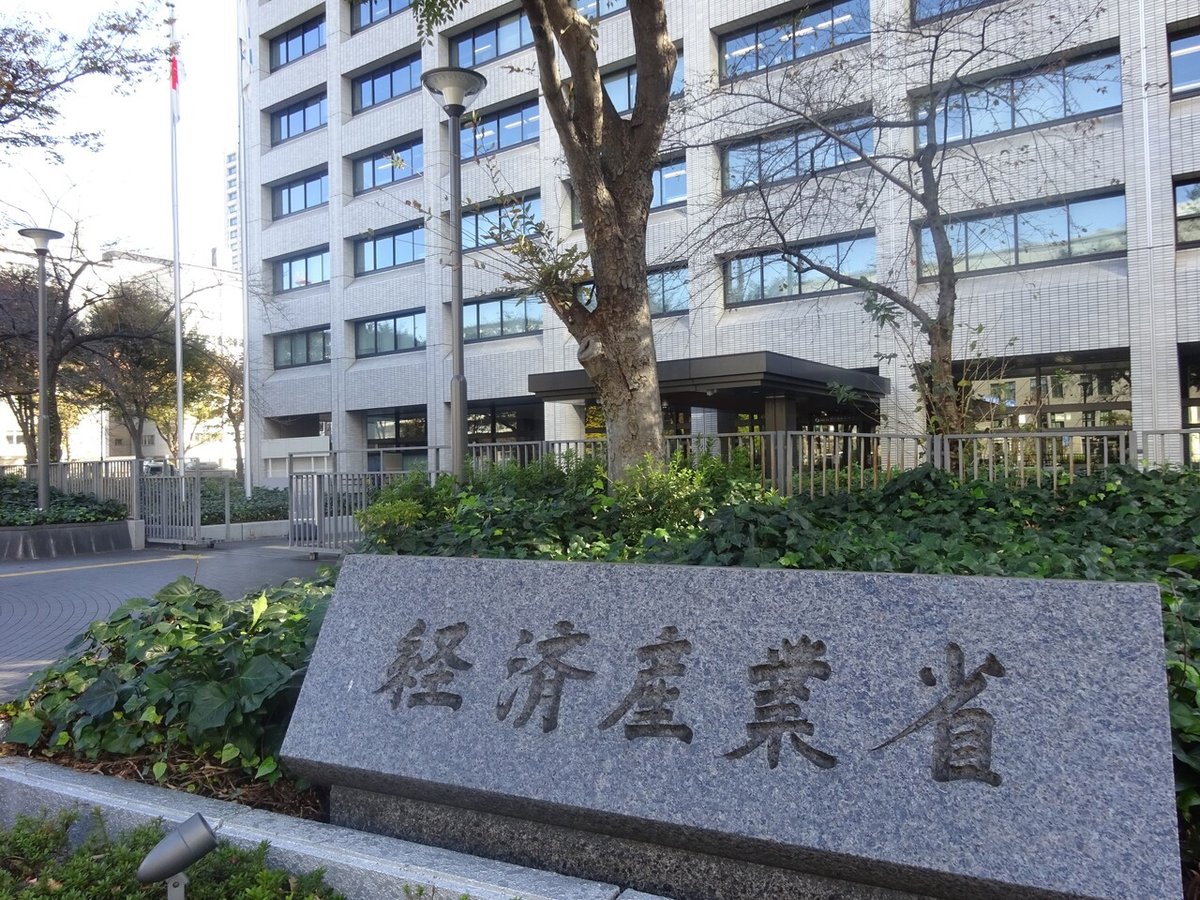
20世紀末から労働の規制緩和が進んで、非正規労働者は4割弱まで高まった。その結果、年収200万円以下で働く給与所得者は1165万人(2020年、給与所得者の22.2%)と、1990年代半ばで最も低かった1998年度の17.5%(793万人)から7%ポイント近く上昇した。大企業・非製造業が最も人件費を削減したのは、非正規労働者を多く採用したからである。
こうした賃金の下落は日本だけではない。ゼロ金利の国であるドイツ、フランスの実質賃金も日本と同様に下がっている。ドイツ、フランスの実質賃金は2001年がピークでそれぞれ8.2%、8.4%減少している(OECDデータ)。それに対して、米国は1.44倍(1990年代半ば以降で最も低い1995年との比較、年率2.4%増)、英国は1.68倍(同1994年比、年率3.5%)だった。これら日独仏と英米どちらも労働分配率は同じように低下していることから、両者の差は金利がゼロかプラスかの違いにある。ゼロ金利の国は成長率が概ねゼロに近いからROEを上昇させるには資本分配率を引き上げる必要があり、その結果、賃金は低下する。
【引き続き「過去の清算―内部留保課税」に続く】
過去の清算―内部留保課税
岸田首相は、11月26日の新しい資本主義実現会議で「来年の春闘では業績がコロナ前の水準を回復した企業は3%を超える賃上げを期待する」と述べた。この発言は安倍政権と同じであって、なにも目新しさはない。さらに、問題なのは来年の賃上げを要請するだけだと、1990年代末から労働生産性の上昇下で実質賃金が低下してきた不当な経営が正当化されてしまう。
日本経団連は2002年12月に「経営労働政策委員会報告」を公表した。同報告書によれば、「企業の競争力の維持・強化のためには、名目賃金水準のこれ以上の引き上げは困難であり、ベースアップは論外である」(第5章の1)と主張している。いわゆる経営者の「春闘の終焉」宣言だった。この報告書には次のような文章がある。「人件費と利益の源である付加価値の向上がなければ、人件費はもとより雇用の保持すら危うくなる」(同報告書、第2章の4)。これは言外に、付加価値が増加する限りにおいては、人件費を増加させるといっているのに等しい。
しかし、経団連が報告書を公表した同じタイミングで日本経済は長期の景気回復期に入り付加価値が増加に転じたが、賃金は現在にいたるまで下落傾向が続いている。経団連は民法の基本原則である「信義誠実の法則(信義則)」(民法第1条第2項)に違反していることになる。経団連がこの報告書を公表した2003年当時は、たしかに大企業の付加価値は1997年度をピークにその後減少傾向が続き、2003年度まで1997年度の水準を超えることができなかった。しかし、2004年度以降2019年度にかけて大企業の付加価値は年1.0%増となっている。

「法人企業統計年報(財務省)」を使って、人件費(従業員給与、従業員賞与、福利厚生費の計)を従業員数でわって一人当たり賃金を計算することができる。全規模・全産業では2002年度(経団連の報告書が公表された年)と比べて2020年度は3.7%減少した。この間、戦後最長と二番目に長い2回の景気回復があったにもかかわらず、賃金は減少している。経団連加盟企業は大企業が多いので、大企業・製造業は同期間で0.3%増に対して大企業・非製造業は7.0%も減少した。
仮に実質賃金が労働生産性の変動率に見合って増減したら、どうなっていたかを「法人企業統計(財務省)」で計算してみると、実質賃金と労働生産性が逆方向に動いた1999年度から 2020年度にいたるまで合計で43.8兆円にものぼる。いわゆる労働者の逸失利益であり、企業からみれば一時預かり金であって利益計上するものではなく、負債の部に引当金として計上すべきだったが、実際には貸借対照表上内部留保金に計上されている。
実は、一時預かり金は賃金だけではない。銀行からの借入金利子率は10年単位で均せばROEと概ね同じになる。経済理論からみても当然同じになる。利子率と利潤率は企業の生産活動によって生まれた付加価値からしか生まれないのであり、両者の源泉は同じだからである。そこで、過去のROEと借入金利子率の関係を金融危機から現在までも続いていると仮定して、銀行への未払い利子額を計算すると、182.5兆円となる。
この差が生まれるのは、銀行への借入金利子率は10年国債利回りと連動しているのに対して、ROEはグローバル展開して外国の成長率と連動するようになったからである。10年国債利回りは向こう10年間の日本の経済成長率を予想して決まっているのに対して、ROEは過去1年間の外国の成長率も加味して決まっている。21世紀になって時間軸も対象範囲も異なるようになったにもかかわらず、銀行への支払い利子率は前例踏襲で決めている。
未払い賃金と銀行への支払い利息を合わせると、226.3兆円(税引き前の段階)となり、これを税引き後に直すと、154.7兆円となって、484兆円の内部留保金に紛れ込んでいることになる。まずは、これまでの20数年間にわたって企業と労働者・預金者の失った利益154.7兆円を返還することが、賃上げをする前にすることである。金融危機以来労働者と預金者が我慢してきた代償を払うことが、経済学の利子・利潤論の原則である。154.7兆円は労働者と預金者が将来を選ばざるを得なかった(企業が倒産しない選択)ことに対する代償なのである。
現在新型コロナによって労働者、預金者、そして宿泊業・飲食サービス業などが大きな打撃を受けているのだから、政府は内部留保金課税によってこれら打撃を受けている人々や企業を「救済」すべきである。労働者や預金者が代償を払ったのは、まさかの時に備えて代償を払ったのであるから、今が返還すべき時期なのである。

賃上げ実現の有効策―ROEサーチャージ課税
過去の清算をしたあとに、賃金は労働生産性基準によって決定することである。
ケインズは資本は人間がつくるものであり、かつ人間は貯蓄超過の性向があるので、資本は過剰になるという。一方、土地は人間がつくれないので絶対的に供給に限界がある。だから、ゼロ金利になれば、資本利潤率(ROE)は土地利回りより低くなって当然だという。10年国債利回りがマイナスになった2016年度以降2019年度(新型コロナの影響がでた2020年度を除く)までROEは年平均で7.6%だった。それに対して土地利回り(REIT)は同3-4%だった。ケインズ理論からすれば、ROEはREITの利回りより低くていいということになる。ROEが3%を超えた当期純利益についてはROEサーチャージ課税をかけることが賃金を上昇させる決め手である。賃上げを実施した企業に優遇税制を実施しても効果がなかったのは事実が証明している。
ROEが3%を超える当期純利益は2016―2019年度の実績から計算すると32.0兆円となる。これにたとえば、75%課税すれば、24.0兆円となる。企業は超過法人税を払うくらいなら、人件費を引き上げるか、下請け会社に対して部品単価の引き下げをしなくなるであろう。仮にサーチャージ課税分がすべて人件費にまわれば、人件費は14.1%アップすることになる。
企業は当然内部留保課税やROEサーチャージ課税に反対するであろう。しかし、資本には二つの機能があることを考えれば、企業の反対は筋が通らない。ゼロ金利になったということは資本が過剰になったことを意味している。資本は二つの機能を持っている。一つは生活水準向上に資する唯物論者の資本であり、もうひとつは救済のために蓄積する資金主義者の資本である(ヒックスの資本論)。前者の唯物論者の資本は有形固定資産で把握することができ、1999年度末の354兆円から横ばいで推移している(2020年度末で333兆円)。生産力としての資本は十分な水準にあるから、20年以上にわたって増えていないのである。
ROE=3.0%という水準は、当期純利益の4割が配当で社外流出したとしても、自己資本の1.8%、金額にして13.6兆円である。日本企業の純投資額は8.1兆円でGDPの1.5%である。企業は純投資のための資金は利益の範囲内で賄えることになり、かつ内部留保金も増加するので借入金が増えることはない。
資金主義者の資本は内部留保金で代替することができる。こちらは、救済のための資本であるが、企業が救済に使おうとしないのであれば、政府が課税するほかない。
<執筆者略歴>
水野 和夫(みずの・かずお)
経済学者、法政大学教授。1953年、愛知県生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。埼玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミスト、内閣官房内閣審議官などを経て現職。『資本主義の終焉と歴史の危機』『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』(共に集英社新書)など著書多数。
この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。
chousa@tbs-mri.co.jp

